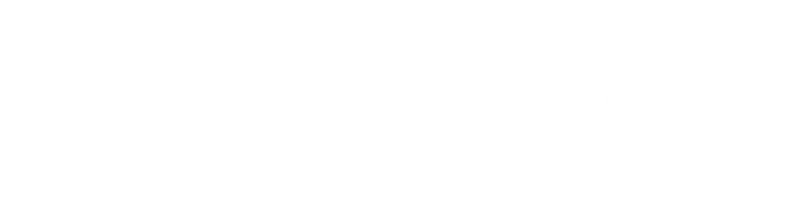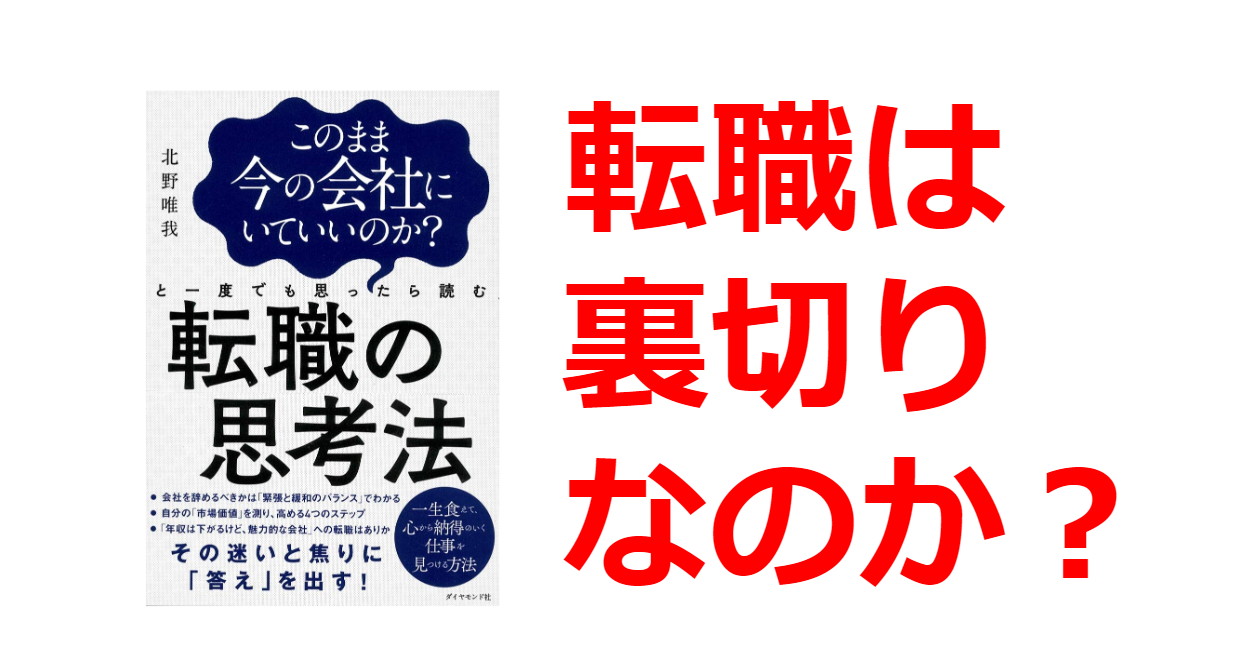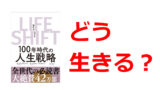どうも、TJです!(自己紹介はこちら)
今回ご紹介するのは、「このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法」です。
本書は物語形式で、転職を考える平凡なサラリーマン青野が、転職コンサルタントの黒岩から転職に対する思考法を教わる、というストーリーになっており、とても読みやすい内容になっています。
その中で、私が特に重要だと感じた3つのポイントについて解説していきたいと思います。
それではさっそく行ってみましょう。
※本記事について解説したYoutube動画もありますので、こちらもご覧ください。
➀転職は悪なのか?
今の会社に不満があって転職をしたいと考えている方は結構な数いると思いますが、なんとなく「転職 = 裏切り」のようなイメージがありますよね。
特に日本はそういった傾向が強い気がしていて、海外に比べて転職経験者の割合が極端に低い、という話をよく聞きます。
果たして、転職は悪いことなのでしょうか?
その問いに対して、本書の中で黒岩はこんなことを言っています。
転職が悪だというのは、新たな選択肢を手に入れる努力を放棄した人間が発明した、姑息な言い訳に過ぎない。
本書 第2章より
この言葉には妙に納得させられました。
日本市場全体で考えれば、転職は悪いことなんかではなく、むしろ人材の流動性が高まり、企業の新陳代謝も良くなって新たな人材が良く育ったりと、良いことずくめだと思います。
ということで、行動せずにいつまでも会社にしがみついてるような人は気にせず、どんどん転職にチャレンジしていきましょう。
また、転職に大事なことは転職サイトに載っている知識や情報ではなく、「どう選べば良いかの判断基準」を持つことだと本書で語られています。
次のセクションで、その前提になる自身の市場価値(マーケットバリュー)の把握方法について解説します。
➁マーケットバリューの測り方
転職を考える人にとって、まず最初に気になるのが「自分の市場での価値」、すなわちマーケットバリューではないでしょうか。
「おれなんて特に人より秀でたスキルもないし、人に自慢できるような成果も上げたことないし、マーケットバリューそんな高くないよな…」なんて思っている人も少なくないと思います。(私も正直自信ありません。)
そこで、本書ではまず、マーケットバリューが何によって決まるのか?かが書かれています。
結論として、マーケットバリューは「技術資産」「人的資産」「業界の生産性」の3つで決まります。
「技術資産」
- 専門性(職種)と経験に分けられる。他の会社で展開できないものは技術資産とはいえない。
- 専門性の例:営業、マーケティング、プログラミングなど
- 経験の例:事業部長の経験、子会社の経営、プロジェクトマネージャーの経験など
- 本書の中では「20代は専門性、30代は経験をとれ」と書かれています。専門性のある人間にこそ貴重な経験が回ってくる、という考え方です。
「人的資産」
- 要するに人脈のこと。自分のために動いてくれる社内の人や、指名で仕事をくれる人を指す。
- 年を増すごとに人的資産の重要性は高まる。
ちなみに、100年時代をどう生きていくかをテーマにした世界的ベストセラー「LIFE SHIFT」に出てくる「生産性資産」「活力資産」は、本書の「技術資産」「人的資産」と重なるところがありますので、気になった方はこちらの記事も併せてご覧ください。
「業界の生産性」
- その業界の人間が平均1人あたりどれぐらいの価値を生み出しているか、ということ
- 業界によっては20倍以上の差がある
- マーケットバリューは業界の生産性に最も大きな影響を受ける
➂ベストな会社の見極め方
自分のマーケットバリューが掴めたところで、次はいよいよ「ベストな会社の見極め方」です。
会社を見極めるポイントと、良い転職エージェントの見つけ方について解説します。
会社選びの3つの基準
本書では、会社を選ぶうえで、以下の3つが重要だと書かれています。
- マーケットバリューは上がるか?
- 働きやすいか?
- 活躍の可能性は十分か?
どれも大事なポイントですよね。
1つ目のマーケットバリューについては、前述した通り「業界の生産性」が相対的に高いか?が重要になってきます。
2つ目の働きやすさについては、会社の採用ページや転職情報サイトを見ると、自分に合った働き方ができるかチェックできると思います。
最近は、週休3日選択制の議論がなされていたり、コロナの影響でリモートワークも一般化してきているので、働きやすい環境がより加速度的に広がっていきそうですね。
3つ目の「活躍の可能性」に関しては、現状のマーケットバリューが高くない人にとっては特に重要だと書かれています。
なぜなら、「活躍の可能性 = 成長の可能性」と言い換えることができ、最終的に「マーケットバリューが上がるか?」という一つ目のポイントに影響してくるからです。
本書では、「活躍の可能性」を確かめる3つの質問が紹介されています。
- 「どんな人物を求めていて、どんな活躍を期待しているのか?
- 「今いちばん社内で活躍し、評価されている人はどんな人物か?なぜ活躍しているのか?」
- 「自分と同じように中途で入った人物で、今活躍している人はどんな部署を経て、どんな業務を担当しているか?」
この3つを聞いたうえで、自分が社内で活躍できるイメージを持てたらOKです。
加えて、「中途を生かすカルチャーはあるか?」「自分の職種が、会社の強みと一致しているか?」といった観点も重要です。
役員が新卒出身者で占められていないか、自分の職種は会社の中で裁量権を得られそうかなど、事前に注意深く確認するようにしましょう。
良い転職エージェントの五箇条
また、ベストな会社を見極めるために、良い転職エージェントを見つけて協力してもらうことも重要です。
以下の5つのポイントを覚えておきましょう。
- 面接時、どこがよかったかだけでなく、入社するうえでの「懸念点」はどこかまでフィードバックしてくれる(こちらから「自分の懸念点はどこですか?」と必ずきくこと)
- 案件ベースでの「いい、悪い」ではなく、自分のキャリアにとってどういう価値があるかという視点でアドバイスをくれる
- 企業に、回答期限の延長や年収の交渉をしてくれる
- 「他にいい求人案件は、ないですか?」という質問に粘り強く付き合ってくれる
- 社長や役員、人事責任者との面接を自由にセットできる
ただ、「採用が決まった時点で企業からエージェントに成果報酬が支払われる」という転職エージェントのビジネスモデルを考えると、注意すべき点もあります。
言い方は悪いですが、とにかくなんでもいいから会社に入れてしまえば、転職エージェントには収益が発生する訳ですよね。
なので、彼らが強く勧めてくる会社は単に採用基準が低い会社、すなわち、彼らからすれば入れやすい会社に過ぎないことも多々あります。
「このエージェント、やたらとたくさんの会社を受けさせようとしてくるな」と思ったら注意が必要です。
また、エージェントから紹介される案件だけで就職先を絞るのもやめましょう。
行きたい会社があるのであれば、その会社の採用ページや転職マッチングサービスなど、あらゆるチャネルを自分で調べることをおすすめします。
まとめ
いかがだったでしょうか?
まずは転職に対するイメージをフラットにして、客観的に自分のマーケットバリューを認識するところから転職活動を始めてみましょう。
本書の中で著者も書いていますが、すべての人が「いつでも転職できる状態」をつくりだすことができれば、一人ひとりの生き方、さらには日本社会も大きく変わるのではないでしょうか。
今回ご紹介した内容はほんの一部なので、興味を持った方はぜひ書店などで手に取っていただければと思います。
ではまた!
👇マーケティング業界への転職をお考えの方は、CMでお馴染みの「RECRUIT AGENT」に登録して求人情報を探してみてください。