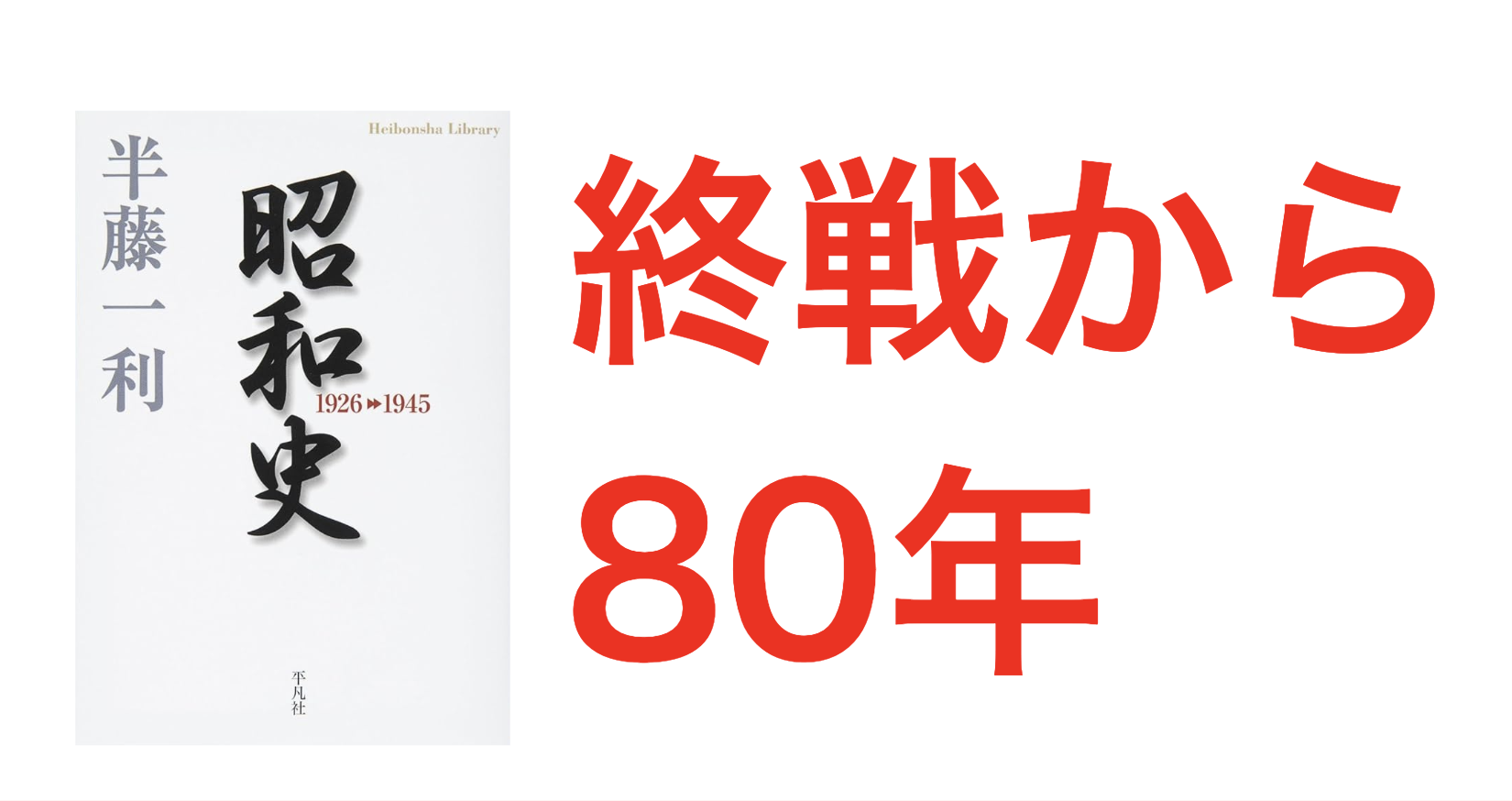どうも、TJです。(自己紹介はこちら)
今日は80回目の終戦記念日。今年は昭和100年、戦後80年にあたる年。
そんな節目となる年を待っていたかのように台頭してきたのが、この夏の参院選を席巻した参政党。
私は、国民の熱狂をこの目で確かめるために、参政党の演説に足を運んだ。そこで感じた熱狂こそ、太平洋戦争に足を踏み入れた当時の人々の熱狂と重なる気がして、何とも言えない危うさを感じた。
参政党の良し悪しについてどうこう言うつもりはないが、戦争の記憶が薄れてきている現代において、改めて昭和を振り返り、「なぜ日本は太平洋戦争に突入し、敗れたのか」を知ることが日本人に必要だと感じた。
私は昭和63年、昭和が終わりを迎える時に生まれ、失われた30年と呼ばれる日本を生きてきた。昭和生まれの端くれとして、次世代に昭和がどんな時代だったかを伝え、同じ失敗を繰り返させてはいけないと感じている。
これからお伝えする内容は、故・半藤一利さんが書かれた「昭和史」から私自身が学んだ内容を基に、概略をまとめたものになっている。本書は半藤さんが読者に語りかけるような表現で書かれているため非常に読みやすく、詳しく昭和史について学ぶことができる傑作である。ぜひ一度手にとって読んでもらいたい。
昭和という時代
昭和とはどんな時代だったのか。
大局的に見ると、明治・大正の帝国主義の流れから突入した太平洋戦争での敗戦、その後の目覚ましい復興と経済成長による栄光という明暗がくっきり分かれた時代だったと言える。
取り分け伝えたいのは、前半部分の「なぜ日本が太平洋戦争に突入し、敗れたのか」ということ。
決して同じ過ちを繰り返してはならないし、太平洋戦争での失敗は平成以降の失われた30年にも通じており、まさに今を生きる我々が学ばなければならない史実だと思う。
なぜ日本は太平洋戦争をはじめたのか
きっかけは幕末のペリー来航:1853年
「なぜ日本は太平洋戦争をはじめたのか」
この問いには人によって様々な答えがあると思うが、発端は幕末のペリー来航であったと私は思う。
この大事件は、250年以上も続く天下泰平を謳歌していた江戸時代の人々に大きなショックを与え、明治維新へと続く流れを引き起こした。
欧米列強からの侵略危機に対して、国内は尊皇攘夷派と開国派に分断され、戊辰戦争・西南戦争という国内最後の内戦を経て、遂に幕府は滅び、明治時代が幕を開けた。
列強入りを果たした明治:1868年~1912年
富国強兵や殖産興業に象徴されるように、明治時代以降の日本国内には、「とにかく欧米列強に追いつけ追い越せ」という空気が充満していた。
その空気が日清戦争へと日本を突き動かし、勝利によって晴れて列強の仲間入りを果たしたことで、日本国民の自尊心は最高潮を迎えていたのだろう。
余談だが、政治の安定に先んじて軍隊の増強を進め、その台頭を許してしまったことが、その後の軍部の暴走に繋がったことを考えると、この時点で1945年8月15日の敗戦が運命づけられていたように思えてならない。
話を戻すと、日清戦争の戦勝ムードに水を差したのが所謂「三国干渉」であり、ここで味わった屈辱によって日本国内では「大陸進出」の機運が高まっていくのである。
そして、打倒ロシアを望む世論の高まりから日露戦争の開戦、勝利へとつながったのだ。
結局のところ、日清戦争以降の日本の戦争というのはロシアに対する防衛戦略上の緩衝地帯、すなわち朝鮮半島を巡る攻防戦であったという側面がある。
民主主義が活発化した大正:1912年~1926年
そして時代は大正に入る。
この時代に起きた世界規模の出来事が第一次世界大戦であり、日本も連合国側として参戦し、戦勝国に名を連ねることになる。
しかし、その後に成立したワシントン体制(東アジア・太平洋地域における国際秩序を維持するために形成された枠組み)によって、日本は海軍軍縮や中国における権益の制限を強いられるようになる。
特に対ロシア防衛と資源確保において最重要である満州での権益拡大を制限されたことは、その後の日本の動きに大きな影響を与えていくことになった。
また、大正デモクラシーと呼ばれる、普通選挙法や政党内閣、治安維持法の成立など、民主主義的な思想の拡がりもこの時代を象徴する大きな出来事であった。
関東軍の暴走と満州支配:1926年~1933年
前置きが長くなったが、いよいよ話は昭和に入っていく。
ここから日本は一気に太平洋戦争開戦までの道を駆け上がっていくわけだが、なぜ日本は無謀な太平洋戦争に突入したのだろうか?
その理由を端的に述べるとすれば、「満洲支配を渇望する関東軍の暴走」「国内政治の腐敗による軍部の台頭」「世論を開戦へと扇動するメディア」「同調圧力によって膨張した国民の熱狂」によるものだったと私は思う。
先述の通り、日本にとって満州はロシア防衛と資源確保の戦略拠点だったのだが、時代が昭和に入ると、中国では蒋介石率いる国民党による国内統一の動きがあり、北伐(同党が編成した軍隊の北上)によって満州支配が脅かされる状況になったのだ。
これに対して満州支配を目論む関東軍は、政府承認を得ずに現地軍閥指導者である張作霖を爆殺する事件を引き起こした。元々、満州駐留の精鋭部隊で、本国からの統制が弱く現地での自律行動が可能な立場だった関東軍はこれに味をしめ、現地判断でことを起こし既成事実化するという行動原理が強まっていく。(これが後の満州事変に繋がっていく)
さらに、1929年に起こった世界恐慌によって農村不況が深刻化したことで、「満洲開発による経済再生」「満州は日本の生命線」という論調が強まった。
そして、1931年9月の柳条湖事件をきっかけとする満州事変が勃発し、翌1932年に日本の実質的な傀儡国家である満州国が建国された。要するに、関東軍が自作自演で南満州鉄道を爆破し、それを中国軍のせいにして、鉄道防衛の目的と称して満州全域を占領したのだ。
国際世論から激しく非難された結果、日本は国際連盟から脱退し、孤立を深めていくことになる。
新聞では、満州事変からの日本政府の動きが異常なまでに賞賛され、これ以降、日本のメディアは世論を開戦へと扇動していくようになるのである。この動きには、軍部が主要メディアを駆使したプロパガンダに本腰を入れ始めたという背景があり、日本国民の熱狂は高まっていった。
国内政治の不安定化とクーデター未遂:1932年~1936年
同じ頃、日本国内では腐敗した政党政治や農村不況に対する不満が募った結果、軍部主導のクーデターが発生した。
1932年に起きた五・一五事件、1936年に起きた二・二六事件である。
いずれも青年将校が武装蜂起し、政府要人を襲撃・暗殺した結果、事実上の軍部独裁体制が確立した。
二・二六事件では、天皇親政の下での国家改造(昭和維新)を推し進めようとした皇道派が粛清され、軍部内の統制を重視する統制派が陸軍を掌握することとなった。統制派の中心人物だった東條英機や永田鉄山らが、ここから台頭していくのである。
日中戦争から太平洋戦争へ:1937年~1941年
運命の一発が引き起こした盧溝橋事件
そして、ついに1937年7月、「運命の一発」と称される銃撃から日中間で勃発した盧溝橋事件をきっかけに、日本は泥沼の日中戦争へと足を踏み入れていくことになる。
日本軍は中国全土に進軍していったが、南京事件(南京虐殺)によって国際的非難が強まった。南京事件の史実については諸説あり、現代でも議論が巻き起こっている。
当初、日本は日中戦争を短期決戦と想定していたが、蒋介石政権の徹底抗戦によって長期戦となり、戦線は膠着状態が続いた。
1939年には、中国を支援していたソ連との間でノモンハン事件が発生。満州とモンゴルの国境地帯で武力衝突した結果、日本はソ連軍に敗北した。
ソ連軍は最新鋭の戦車や機械化部隊を配備しており、この敗北でソ連との正面戦争は困難という認識が陸軍内に広がったことで北進論(ソ連に進出して資源を確保する戦略)が後退した。
第二次世界大戦の勃発と枢軸化
時を同じくして、国際情勢にも大きな動きが起こる。
日本の後を追うように国際連盟を脱退したドイツがポーランドへの侵攻を開始、第二次世界大戦が勃発したのだ。
ドイツが西欧を制圧し、フランスやオランダの植民地防衛力が低下したことを受け、日本は仏印(現・ベトナム)に進駐し、南進への足掛かりを得た。
そして、1940年の日独伊三国同盟締結によって、日本は名実ともに枢軸国の一員になったのである。
日中戦争の泥沼化で窮地に立たされる日本軍
泥沼化する日中戦争を継続するため、特に石油確保を目的とする南方資源地帯の掌握に唯一の活路を見出した日本軍は、日ソ中立条約締結によって北方の安全を確保した上で、南進に集中する決断をする。
日本のさらなる南方進出に対し、いよいよ米英は経済制裁を強化。1941年7月には米国が在米日本資産を凍結、石油禁輸を実施したため、石油輸入量の約8割を米国に依存していた日本の石油備蓄量は1~2年で底をつく状況だった。
窮地に追い込まれた日本軍は「資源確保のための行動が不可避」との認識を強め、対米交渉による解決を模索しつつも、同時に南方作戦準備命令を発出し、交渉に失敗した場合は武力行使も辞さない構えだった。真珠湾攻撃もこの文脈で立案された。
対米交渉の決裂で開戦を決意
しかし、その後の対米交渉は思うように進捗せず、日本から提示された妥結案は受け入れられなかった。
そして11月26日、米国から所謂「ハル・ノート」が提示された。そこに記載されていたのは、「中国・仏印からの無条件撤兵」「日独伊三国同盟の実質破棄」「満州国否認」といった日本には到底受け入れ難い内容だった。
日本政府はこれを実質的な「最後通牒」と受け止め、開戦を決意するに至ったのである。
終戦への道
真珠湾攻撃成功と快進撃:1941年~1942年
開戦の決意に先んじて連合艦隊が編成した真珠湾攻撃部隊は、ハワイ島の真珠湾に向けて択捉島単冠湾を出港した。
連合艦隊司令長官山本五十六によって立案されたこの作戦の狙いは、先制攻撃によって米国に致命的なダメージを与え、即座に講和に持ち込むことだった。
12月1日の御前会議で対米英蘭戦争開始が正式に決定。開戦日は12月8日に設定された。
そして、日本時間8日未明、真珠湾攻撃を敢行。米太平洋艦隊主力に打撃を与え、作戦は成功した。
だが、日本の狙いとは裏腹に、この奇襲攻撃が、それまで孤立主義(モンロー主義)を貫いていた米国の戦意に火をつけてしまった。「リメンバー・パールハーバー」を合言葉に、米国は太平洋戦争、ひいては第二次世界大戦への本格参戦を決意したのである。
太平洋戦争勃発と同時にマレー半島・フィリピンなどへ進軍した日本は、その後も破竹の進撃を続け、資源地帯を次々と手中に収めていった。日本の快進撃を大々的に報じる新聞は飛ぶように売れ、各社が競って戦地の状況を伝えたことで、国民の熱狂は最高潮に達した。
ミッドウェー海戦での形勢逆転と戦局悪化:1942年~1944年
しかし、ミッドウェー海戦で流れが変わる。
日本の主力空母4隻が海に沈み、戦局は守勢へと傾く。
ガダルカナル島の戦いでは、日本軍は補給もなく持久戦を強いられ、撤退を余儀なくされた。
もちろん、この事実が日本国民に知らされることはなく、軍部はメディアと結託して国民を欺き続けた。
1944年6月にはサイパン島が陥落し、日本本土が爆撃圏内に入ったことで、本土空襲が激化していった。
10月のレイテ沖海戦で日本海軍が壊滅したことで、日本軍は制海権・制空権を喪失した。
本土空襲の激化と原爆投下、そして終戦へ:1945年
1945年3月10日の東京大空襲では首都東京が甚大な被害を受け、4月から始まった沖縄戦でも激戦の末、軍人・民間人かかわらず多数の死者を出した。
そして8月6日に広島、8月9日に長崎と立て続けに原子爆弾が投下された。
なす術がなくなった日本は8月15日、ポツダム宣言を受諾し、終戦を迎えた。
軍人・民間人合わせて300万を超える死者を出した、紛れもなく日本史始まって以来の悲劇だった。
なぜ昭和史を学ぶのか
ここまでの流れを大局的に振り返ってみたい。
ペリー来航に端を発する外的圧力によって日本国内が分断され、紆余曲折を経てナショナリズムを掲げる勢力が台頭し、メディアを駆使したプロパガンダによって熱狂した世論が同調圧力に支配され、ガバナンス不全に陥った政府が冷静な判断力を欠いた結果、負けると分かっていた戦争に足を踏み入れてしまったと回想できる。
これを、現在の日本に置き換えてみるとどうだろう。
グローバリズムを推し進めた結果、外国人問題が国内で取り沙汰され、日本ファーストを掲げる参政党が、SNSを主とするメディア戦略によって支持を拡大したことで、多党化した政府が判断力を失なおうとしている。
この状況に危機感を抱くのは私だけだろうか。
私は、今回の参院選において、一時、参政党への投票を真剣に考えていた。
なんとなく、今の与党では心許ない気がするし、政治に刺激を与える意味でも、参政党による大きなムーブメントに期待する気持ちがあった。
だが、一連の参政党に関する報道や足を運んで見た演説を通して、上述のような「危うさ」を感じ、結果的に投票はしなかった。繰り返しになるが、参政党自体の批判や政策の良し悪しを論じる意図は私にはない。
ここで大事なことは、過去の歴史と照らし合わせた上でアナロジー的に違和感を覚えた結果、投票を踏みとどまる意思決定をした、という部分にある。
つまり、同調圧力や世論が醸し出す「空気」に身を任せて熱狂するのではなく、事実を知った上で自らの頭で冷静に考え、自らの行動を判断することが重要なのだ。
「昭和史」の中でも、著者の半藤さんは次のように書いている。
国民的熱狂をつくってはいけない。その国民的熱狂に流されてしまってはいけない。
ひとことで言えば、時の勢いに駆り立てられてはいけないということです。熱狂というのは理性的なものではなく、感情的な産物ですが、昭和史全体をみてきますと、なんと日本人は熱狂したことか。
マスコミに煽られ、いったん燃え上がってしまうと熱狂そのものが権威をもちはじめ、不動のもののように人びとを引っ張ってゆき、流してきました。
昭和史 戦前篇 1926-1945 「むすびの章」より引用
毎年この時期になると、「同じ過ちを繰り返してはならない」「戦争は絶対にしてはいけない」という発信が至る所で繰り広げられるが、過去の歴史を学ばなければ、そういったメッセージは意味をなさない。
次世代の日本人が同じ失敗を繰り返さないためにも、私は自ら歴史を学び、それを特に自分より若い人たちに伝えていきたいと思う。
ではまた。